| テーマ | 「都市」 |
|---|---|
| 審査員 | 児島 やよい、清水 敏男、土屋 公雄、中山 ダイスケ、八谷 和彦 |
| 賞 |
グランプリ(賞金100万円)───1点 準グランプリ(賞金50万円)───1点 入選───4点 |
| 応募期間 | 2012年5月17日(木)~6月7日(木) |

グランプリ(賞金100万円)
【受賞者】
太田 遼 アーティスト
東京都出身、在住
【受賞作】
「中に入れてくれ」、と屋外は言った。


準グランプリ(賞金50万円)
【受賞者】
宮本 宗 アーティスト
三重県出身、愛知県在住
【受賞作】
風景「都市と生きる」

都市の独特の空気のなかで感じる違和感は、自分自身がその膨大すぎるエネルギーの中に飛び込んだときの圧迫感であるように感じる。都市にはエネルギーという目に見えない力がいたるところに及んでおり、私達はそれらが秘めるリスクを無意識に背負いながら日々を生きている。そんな私達の生き方はどこか滑稽であるように思う。
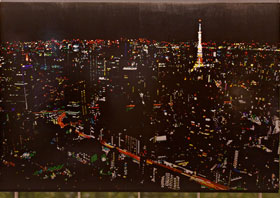
入選
【受賞者】
大村 雪乃 学生
中国出身、東京都在住
【受賞作】
Beautiful midnight
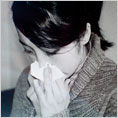
この夜景は文房具シールだけで作られています。モチーフとなった景色は東京ミッドタウンに隣接するホテル、ザ・リッツ・カールトン東京のある一室からの眺望です。
灯り一つひとつを安価な素材であるシールにおきかえ大量に用いて、都市の灯りを表現することで、夜景の美しさと金銭価値のギャップ、また大量消費社会の違和感を表現し、そして六本木を訪れる多くの方に節電や環境について考えるきっかけにしてもらいたいです。

入選
【受賞者】
角 文平 造形作家
福井県出身、東京都在住
【受賞作】
一戸建てマンション

本来、何者にも侵略されることのないプライベートな空間であるべき人間の住居は、人口が過密化している現代都市の中において互いにテリトリーを切り詰め、極限まで隣接しあわなければいけない状況にある。不快なまでの密接な距離感は、互いにバランスをとるためにあえて干渉し合わず、希薄な人間関係を生み出しているように思う。一定の距離を保つためにグリットに固定された家々は、今日も上へ上へと積み重ねられていく。

入選
【受賞者】
下平 千夏 美術作家
長野県出身、東京都在住
【受賞作】
To-kyo

止まることを知らず、すべてを飲み込み回り続ける都市/東京。
この混沌とした見えない「力」と、それに飲み込まれていく「時間」を表出する。
本展のテーマである「都市」を、自分自身が最も知り得ている「東京」と捉え、体験の中から"To-kyo"という名の自我を持つモンスターを想定し、本作品を構想した。
モンスターは時間を食し、力を産み出す。我々はそのモンスターを構成する細胞核であり、この作品は、モンスターの力そのものを表現している。
制作協力:アイダエンジニアリング株式会社 伊藤隆夫、内田康幹、渡辺隆男
吉成工業株式会社 吉成隆

入選
【受賞者】
林田 健 絵描き
愛知県出身、在住
【受賞作】
昨日は明日とどれだけ違うのだろうか。

過去から現在までの人の痕跡を物質の中に見出し、そこから未来を見つめていきたいと思います。
絵が持つprimitiveな力を信じてrebel paintingを以って立ち向かいたい。



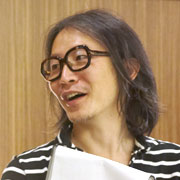


今年度のテーマは昨年に引き続き「都市」。東京ミッドタウンを代表するパブリックスペースであるプラザB1Fメトロアベニューでの展示プランを応募条件とし、総計241作品の応募がありました(応募条件は39歳以下、かつ1名(組)1作品案まで)。今年度はテーマ性とともに、公共性の高い「場」の特性を活かそうとする大胆かつ意欲的な作品が目立ち、ジャンルも立体、インスタレーション、平面と多岐に渡り、例年にも増してハイレベルな戦いとなりました。「コンセプト」「場所性」「芸術性」「現実性」「独創性」を審査基準とし、一次審査で12作品を選出。二次審査ではそれぞれの作家が模型を使って公開プレゼンテーションを行い、昨年より2点増やした計6点の入選作品を選出しました。通過者6名には制作補助金として100万円が支給され、2012年10月6日(土)より公開制作を実施。10月15日(月)の最終審査にて、グランプリ1作品、準グランプリ1作品、入賞4作品の各賞が決定しました。今回は本コンペ初の平面作品が2作品入賞したことも特筆すべき点です。ジャンルに関わらず、多くの人の目に触れるパブリックな空間に、独創性と現実性を併せ持つ提案ができたかどうかが、審査の明暗を分けたと言えます。6名の受賞者に大きな拍手を送るとともに、今回ご応募いただきましたすべての皆さまに、心より感謝申しあげます。





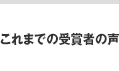

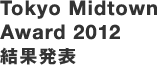




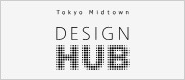

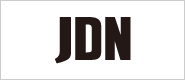
屋外は思いました。自分だって中に入りたい。
そこで、思い切って中に入ってみました。
やっとのことで中に入った、その様子を見た通りがかりの人が言いました。
「こんなところに屋外がある」
屋外はやっぱり屋外なのでした。