
TOKYO MIDTOWN AWARD 2025アートコンペ結果発表
アートコンペ概要
| テーマ |
応募者が自由に設定
東京ミッドタウンという場所を活かしたサイトスペシフィックな作品を募集します。 |
|---|---|
| 審査員 | 金澤 韻、永山 祐子、林 寿美、ヤノベケンジ、脇田 玲 |
| 賞 |
グランプリ(賞金100万円 + トロフィー)─── 1点 準グランプリ(賞金50万円 + トロフィー)───1点 優秀賞(賞金30万円 + トロフィー)─── 1点 ファイナリスト(3組)には表彰状を贈呈
|
| 応募期間 | 2025年4月21日(月)~5月12日(月) |
| 応募総数 | 303点 |
My Gaze, My Choice.
-

-
受賞者:
- リブ
- アーティスト
- 素材:義眼、義眼用金属フラスコ、55インチモニター

- 協力:アートアイ・ラボ
まなざしを選ぶ行為は、選択の自由を取り戻すこと。選択肢ごと覆い隠されてしまう社会では、義眼に限らず、性別・障害・年齢・出自・容姿・犯罪被害など、多様な人々の「在り方」に視線が重くのしかかる。
そのまなざしは誰のものか? 「かわいそう」「こわい」「普通じゃない」と決めるその視線は?
なぜ自分の在り方を他者の視線で決めなければならないのか?
この作品は通りすがりのあなたに問いを手渡し、選ぶ自由を差し出す。
金澤 韻 講評
どうしても言わなければいけないことがあるということと、それをどうしたら伝えられるのかということを、考え続け、工夫し続けてきた人の表現でした。4つの映像を並べようとした初期案から、義眼作品の新作を制作しその現物を展示、また内容を把握しやすいよう、新規で撮影した映像を組み合わせたインスタレーションに変更してきた点も、テーマの強さに頼らずに伝えようとする正しい戦略があり、その創意と意欲が高く評価されました。
永山 祐子 講評
リブさんの作品は荒削りながら強く訴えかけるものがあった。彼女が発信したい社会的マイノリティーの精神的な解放、そして閉じた義眼の世界への疑問、未来を変えていきたいという強い希望が、アートの世界でこそ自由に発信ができることを知り、活動をはじめたという。アートは何のためにあるか、そのことを5年間、この賞を通して考えさせられてきた。その答えは様々あると思う。その一つの答えを彼女の作品は持っていたように思う。強い動機と意志を持つリブさんはこれから進化を遂げていくだろう。その背中を強く押したいと思った。
林 寿美 講評
自身の「義眼」をモティーフにするという難問に果敢に挑戦し、主体と客体のバランスを巧みにとって見事に作品に昇華されていただけでなく、本来伝えたいメッセージもストレートに表現されていたと思います。社会を動かし人々の価値観を変えるというアートの役割が、この作品を通じて必ずや発揮されることでしょう。今後の作品の展開にも期待しています。
ヤノベケンジ 講評
彼女の制作は自己表現を超え、公益的理念と意思を優先する姿勢がそのままアイデンティティとして強固に存在している。作品は今後さらに饒舌な表現へと展開する可能性を秘め、アートの役割や使命を力強く示唆する。その確信に満ちた在り方に圧倒され、深い感銘を受けた。
脇田 玲 講評
「メディアとは身体の拡張である」というメディア論の現在点を示す作品です。作家のリブさんは極度の特異性をアイデンティティとして捉え直すことで、アートが生の居場所になりうることを発見しました。ステラークやジョー・ディヴィス、スペキュラティブデザインに基づく欧米的なバイオアートとは全く異なる態度を感じました。本作のインスタレーションは工芸やブランド品のあり方にも問題を提起しており、消費文明の射程には含まれることのない存在について、また、包摂的な社会は果たして可能なのか、改めて考えさせられました。
振る舞いの機微
-

-
受賞者:
- 山﨑 結以
- 画家
- 神奈川県出身
- 素材:絹本着色

幼少期を「社会性の学び始め」と捉え、集団行動のなかで表れるそれぞれの振る舞いの機微を描くことで、価値観の異なる他者とともに生きていくこと、という普遍的なテーマに触れています。
排他的な空気が広まる現代を生きる中で、他者との関わりについて想像し学ぶことの重要性を強く感じています。
絵の中にかつての自分や誰かの面影が重なり、思いを巡らせる時間を過ごしていただけたら幸いです。
金澤 韻 講評
絵画作品の展示には必ずしも向いていない東京ミッドタウンのコンコースですが、しっかりとした画力による絹本による日本画が、ゆるぎのない、凛とした空気感を作り出していました。子供たちの視線は、ピュアでありつつも集団の中に置かれ、自己世界と社会のみぎわを静かに漂います。これを見ていると、その瞳のどこかに自分や友達の面影を重ねてしまうのです。パブリックスペースにふと空いた、パーソナルなポケットへ潜り込むような、印象的な鑑賞体験を生み出しました。
永山 祐子 講評
山﨑さんの作品は一次審査の時から一番好きな作品だった。絵のうまさ、古典技法を駆使した表現力、その上に彼女の絵の持つ独特な世界観。作品としての完成度の高さは群を抜いていた。今回選んだモチーフの幼少期の集合写真は東京ミッドタウンの喧騒の中、異様な静けさを持っていた。一瞬のっぺらぼうなのかなと思い近づいていくとそれぞれの顔の表情が徐々に見えてくるという遠景と近景のバランス。これからがとても楽しみな作家である。
林 寿美 講評
日本画の技法を使いながら、日本画らしくない作品に、しかも現代美術の文脈のなかで仕上がっていたこと、さらには、子どもたちの表情の見せ方や色づかいなど、往来の多い東京ミッドタウンでどのように人々の目を惹きつけるかを熟慮した表現になっていたことを高く評価したいと思います。
ヤノベケンジ 講評
その画力は日本画の技巧を深く探究し尽くし、現代の表現へと洗練させている点に強く心を打たれる。作品の存在感は公共の通路空間にも的確に響き、あらゆる表現現場に応答し得る豊かな可能性を示す。今後さらなる展開が期待される作家である。
脇田 玲 講評
遠目には未完成のように感じる作品ですが、近づいてよく見てみると、とてつもなく繊細な描画がなされており、同時にとても考えられた構図であることがわかります。三十三間堂を思わせる配列と存在の境界が曖昧な幽霊画のようなタッチからは日本美術からの確かな系譜を感じます。最前列の子供の手の描画にはマンガに通底する形を感じつつも、その透明感に吸い込まれそうになります。超絶技巧に裏打ちされた新しい日本画に圧倒されました。
nemui
-

-
受賞者:
- 岡田 希乃風
- 作家
- 千葉県出身
- 素材:ミクストメディア

寝る前、支度を済ませてもう目を瞑るだけ…でもついスマホを見てしまう。誰しも心当たりがある瞬間に焦点を当てた。何もないように見える寝る前の時間には安心感や孤独、外では見せない素の感情が浮かぶ。言葉にしにくいその感情を、一目ずつ編み重ねて形にした。編むという行為は、私にとっては時間を編むことでもある。人が行き交う都会だからこそ、この瞬間をくり抜いて形にする意味があると思っている。
金澤 韻 講評
この作家にしか出せない味わいが確かにあります。ただ、すべてご自身の手で作っているにもかかわらずブランケットや服は既製品に見えますし、髪の毛は毛糸そのままでゆるい印象。通路側に背中を向けた配置によって、手元の見事に作り込まれたスマホなどもあまりよく見えません。支持体の工夫など、見せるための戦略を考えるように助言していましたが、そのままでした。今後もマイペースに創作を続けるのでしょうか。そっと応援しています。
永山 祐子 講評
岡田さんの作品は一次審査の時からとても気になる作品だった。東京ミッドタウンに置かれた作品は、煌びやかな東京ミッドタウンと家での怠惰な自分の生活シーンというコントラストによって、圧倒的な存在感を放っていた。見ているとどこか共感を持て、思わず触れてみたくなる。そんな風にいつの間にか鑑賞者が巻き込まれている。人を引きつけ巻き込む力を持っている作家であり、これから表現を磨いていくことでさらに良い作品がうみ出されて行くことを期待している。
林 寿美 講評
六本木という日本で最も先端的な街にある東京ミッドタウンだからこそ、作品の異様さが際立ち、見た人をくすりと笑わせながらもシニカルにも見える作品として成立していました。また、AIが人間の領域を侵食しつつある現代において、手でものを作る喜びやそれにかける情熱を感じさせてくれました。作品を見た人たちの反応がどのようなものになるのかも楽しみです。
ヤノベケンジ 講評
クラフト的手作業の細部はユーモアを宿し、見る者の目を愉しませると同時に驚きを誘う。東京ミッドタウンに最も不釣り合いな人間の怠惰を描き出し、その批評的精神に鮮烈さを感じる。無限の展開を秘めつつ、深刻な現代世界に安堵と癒しをもたらす作品である。
脇田 玲 講評
自室で眠っている様子を手編みで表現した作品とのことですが、東京ミッドタウンに置かれたその姿、私にはホームレスに見えたのです。「ゆるふわ系」のリラックスできる自室(Homeness)をパブリックな場にインストールすることで、都市部から排除されがちな存在、すなわちホームレス(Homeless)のイメージが立ち現れるように感じたのでした。作家の意図であったのならば大したものです。地球上のすべての人々が心からリラックスできる「自室」を獲得できる日は訪れるのでしょうか。
growth ring
-

-
ファイナリスト:
- 岩佐 美和子
- デザイナー
- 大分県出身
- 素材:プラスチック、アクリル板

旧防衛庁から東京ミッドタウンへの変遷を見てきた木の年輪を表現しました。
年輪の何も無い部分を破壊という行為により描くことで形成された経緯を見ます。
水や養分の運搬、成長の度合いや年月から得られた「無」から遺った部分は乱反射を起こし、破壊前よりも光りを集め輝き可能性を感じさせます。
無いものを見て意味の無さそうな行為を続けることで、意味や可能性を見出すという経験から形成された作品です。
ヤノべケンジ 講評
緻密な手作業の蓄積が作品に独自の力と強度を与え、植物の成長細胞を表現している意味合いから普遍的な真理を垣間見せている。素材を熱で溶かし接着しながら描写する行為は、作家の情熱を媒介し、その姿勢に深い好感を覚える。さらに公共空間に調和しつつ親しみやすい表現へと昇華されている。
Generated Pimples
-

-
ファイナリスト:
- 善養寺 歩由
- アーティスト
- 東京都出身
- 素材:看板、AI画像、モーター、アクリル板、ラテックス、Arduino、展示台、照明

メディアにおける女性像の記号化と、表象の欠落を主題としたインスタレーション作品。
修正やフィルターによって消し去られるニキビを機械化させた「ニキビマシン」とAI画像を対比させることによって、現代までの販売、消費行動を促すための媒体において好まれる「若く美しいマジョリティ女性のイメージ」の氾濫に問いを投げかける。
金澤 韻 講評
AI生成された若い女性の写真に目を引かれて観察すると、顔には穴が開き、床面には穴と同じ位置でニキビ(のようなもの)が絶えず隆起を繰り返しています。「みなさんはこういうのが好きでしょ」とAIが作り出す虚像に差し込まれる、物理的でリアルなニキビがなんだかおかしく、同時に、見た目に価値を置いてしまう私たち自身も滑稽に思えてくるという、シャープな批評と、面白さのある作品でした。
Torch Interval
-

-
ファイナリスト:
- 𠮷田 桃子
- アーティスト
- 兵庫県出身
- 素材:<平面作品>キャンバス、アクリル絵具
<立体作品>木、石、ステンレス、アクリル絵具

肖像画と調度品を組み合わせた展示形式を、東京ミッドタウンという空間で再解釈し、新たな物語の創出を試みます。登場人物は特定のアイデンティティから解放された流動的な存在であり、彼/彼女らが暮らす海沿いの遺跡は、私自身の記憶や空想が織り混ざった心象風景の断片です。彼/彼女らは現実から離脱する為の儀式として床に紋様を描き、調度品や装飾品を作っています。その架空の儀式は私自身の「創造」の原点を象徴します。
林 寿美 講評
絵画のなかの幻想的な世界とベンチがあるこちら側の現実世界との交錯が肝になる作品でありながら、今回はその関係性がやや弱かったように感じました。その卓越した描写力と画面構成力、個性を生かして、次のフェーズに進み、21世紀のシュルレアリスムともいうべきスタイルに到達されるのを楽しみにしています。
審査員総評
-

-
金澤 韻
(現代美術キュレーター)ファイナルまで残らなかった作品プランの中にも、メンションしたいものが多かった今回の審査でした。落ちてしまった方も、単に機会との相性が合わなかっただけと思っていただきたいです。きっと別の場所で会えるはず。そして、そんな中でも勝ち上がってくるプランは、多かれ少なかれ自分が本当に言いたいことに向き合った、オーガニックな表現が多かったように思います。いっぽう、全体に、驚かされるような作品が少なく、審査員としては投げかけに不足があったか…と自分自身を振り返りました。
-

-
永山 祐子
(建築家)一次審査の段階ではやや例年に比べて印象に残る作品が少なかったが、ニ次審査のプレゼンテーションでは、力強い作品が最終審査に残った。例年、最終審査はとても悩むが今年は早めに決まった。その思いはそのまま最終的な結果に結びついた。最終審査で私が大切にしたことは今年の賞を通してどんなメッセージを投げかけられるか、だった。例年そのように考えてきたわけではなく、今年私がグランプリに選んだリブさんの作品がそのような性質を持っていたことに起因する。最終年の今年、そのような作品に出会えたことは審査員を務めた5年間の最後の思い出として印象深いものとなった。
-

-
林 寿美
(インディペンデント・キュレーター)現代における創造とは何なのかー。今回のTOKYO MIDTOWN AWARD アートコンペでの審査で、最初から最後まで考えさせられたのはこのことです。人間はこれから一体どんなものを生み出せるのか。私たちはどんな作品に心を震わせ、豊かな気持ちになるのか。価値観が揺らぐこの複雑な時代、アートに何が求められているのか。ファイナリスト6名の作品から、皆さんひとりひとりがそうしたことに思いを巡らせてみていただければと思います。
-

-
ヤノベケンジ
(現代美術作家/京都芸術大学教授/ウルトラファクトリー・ディレクター)今年の最終選考作品6点は、いずれも異なる方向性を鮮やかに示し、完成度においても高い水準を誇りました。多様性は現代美術の可能性を体現し、単純な比較を超えるものでした。さらに公共空間への応答性も真摯であり、このアワードが教育的視点を備えていたことを証明しました。二次審査以降の試行錯誤が成果として示された点は、誠に喜ばしいものといえます。
-
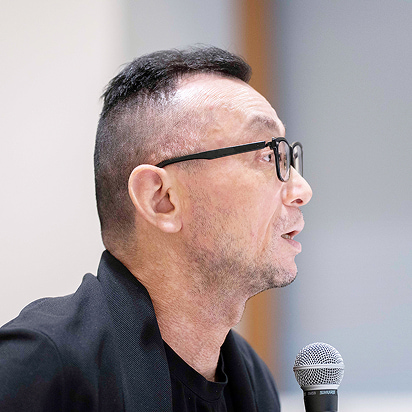
-
脇田 玲
(アーティスト/慶應義塾大学教授)今年のファイナリスト作品はいずれも異なる方向性を持ち、単純な優劣を測れない難しさがありました。最終的には、2025年を色濃く反映した作品や未来の青写真になりうる作品が選考されたと思います。身体と機械の境界が曖昧になる時代での人間性とは何か。生成AIにより「知性」がコモディティ化するなかで手仕事や技巧に宿る「手性」への希望。混乱する移民政策やナショナリズムのうねりのなかでの日本的価値(JAPAN VALUE)とは何か。受賞作品にはそのような2025年現在の問いや未来への希望が託されています。
審査風景
パートナー賞
受賞者・ファイナリストの中からパートナー企業・機関が選出した方へ、副賞としてパートナー賞が授与されます。
パートナー:三井デザインテック株式会社
受賞者: 山﨑 結以《振る舞いの機微》
内容: 三井デザインテック本社での作品展示
村元 祐介(三井デザインテック株式会社 代表取締役社長) 講評
私ども三井デザインテックは、空間創造を通じて「くらしと社会の未来をつくる」という理念のもと、日々事業に取り組んでおります。本作品は、価値観の異なる他者との共生を深く見つめ、その卓越した芸術性と相まって、私どもが志す多様な人々が心豊かに暮らすウェルビーイングな空間に新たな視座と可能性をもたらすものと期待し、本賞を贈呈いたします。


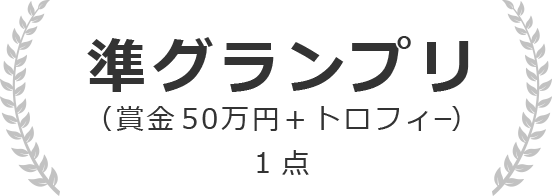
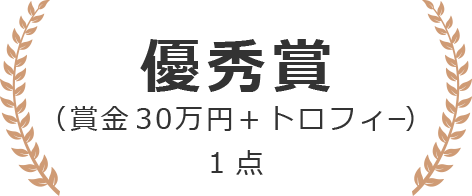
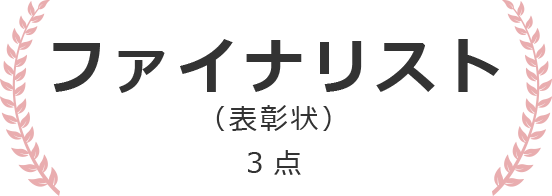








アートコンペ総括
アートコンペでは、テーマは「応募者が自由に設定」とし、東京ミッドタウンを代表するパブリックスペースであるプラザB1を舞台に、場所を活かしたサイトスペシフィックな作品を募集。18回目となる今回は総計303作品の応募がありました。(応募条件は39歳以下、かつ1名(組)1作品案まで。)
審査は前年度と同様に5名の審査員の方々により、「コンセプト」「場所性」「芸術性」「現実性」「独創性」の5つの審査基準で進められました。
また、本年度から賞の構成が変更となり、グランプリ1点・準グランプリ1点・優秀賞1点の計3作品を選出し、その他の3組についてはファイナリストとして位置づけるかたちとなりました。
一次審査では、書類審査で選出された作品の中から、12作品を選出。二次審査では、模型や参考作品を持ち寄った作家たちと審査員が一同に会する中で審査が行われ、最終審査に進む6作品を選出しました。二次審査通過者6組には制作補助金として100万円が支給され、2025年9月16日(火)より作品設営を実施。9月22日(月)の最終審査にて、グランプリ作品、準グランプリ作品、優秀賞作品を選出しました。グランプリに輝いた作品は、作家自身の課題意識を東京ミッドタウンという公共空間でインスタレーションとして発信する強い動機と創作意欲が高く評価されました。
今年度はインスタレーション作品の応募が最も多く、続いて立体、絵画の順となりました。地域別では関東圏からの応募が最多で、近畿・中部がこれに続き、応募者の平均年齢は28.3歳でした。作家たちは自身の表現を東京ミッドタウンという場に重ね、新たな価値を模索。その過程では審査員による白熱した議論が交わされ、最終的に最終審査に進む6作品が選出されました。各審査員の中でも東京ミッドタウンが掲げる「JAPAN VALUE(ジャパンバリュー)」とは何かをあらためて問い直す審査会となりました。
さらに、この度、受賞者およびファイナリストの中から選ばれた方に、パートナー企業・機関より副賞が贈られる「パートナー賞」を新設しました。本年度は、アートコンペのパートナー企業としてご参加いただいた三井デザインテック株式会社より、《振る舞いの機微》を制作された山﨑結以さんに対し、パートナー賞が授与されました。
3名の受賞者には大きな拍手を送るとともに、ご応募いただきましたすべての皆様に、心より感謝申しあげます。